 ホ短調という調性は、ベートーヴェン等の独墺系先進国の交響曲には少ないが、チャイコフスキーの〈5番〉と、ドヴォルザークの〈新世界〉という先例があるので、スラヴ系交響曲の王道を選んだことになる。共に、循環主題で全4楽章を統一するというシンフォニックな構造にこだわったこの2曲が、〈運命〉のリズム主題と、〈幻想〉のイデー・フィクスを両親とする第一世代とすれば、この〈2番〉は第二世代。〈1番〉で辛酸を舐めたラフマニノフが、交響曲作家としての真価を問うべく、論理的構築性を徹底的に追究して仕上げた骨太の大作なのだが、ある時期からカットだらけの短縮版の演奏が当たり前みたいな状況が続いたせいもあって、映画音楽的なロマンティシズムのほうが全面に押し出されることになった。
ホ短調という調性は、ベートーヴェン等の独墺系先進国の交響曲には少ないが、チャイコフスキーの〈5番〉と、ドヴォルザークの〈新世界〉という先例があるので、スラヴ系交響曲の王道を選んだことになる。共に、循環主題で全4楽章を統一するというシンフォニックな構造にこだわったこの2曲が、〈運命〉のリズム主題と、〈幻想〉のイデー・フィクスを両親とする第一世代とすれば、この〈2番〉は第二世代。〈1番〉で辛酸を舐めたラフマニノフが、交響曲作家としての真価を問うべく、論理的構築性を徹底的に追究して仕上げた骨太の大作なのだが、ある時期からカットだらけの短縮版の演奏が当たり前みたいな状況が続いたせいもあって、映画音楽的なロマンティシズムのほうが全面に押し出されることになった。
 魔都、サンクト・ペテルブルク
魔都、サンクト・ペテルブルク この曲、スコアに掲載されたクラウセッティの怪奇趣味的な詩と、レスピーギが付けた音楽の間に大きな開きがあるので、そのあたりを念頭に、お読み頂きたい。
この曲、スコアに掲載されたクラウセッティの怪奇趣味的な詩と、レスピーギが付けた音楽の間に大きな開きがあるので、そのあたりを念頭に、お読み頂きたい。 1880年1月4日~5月15日(この稿の表記は、すべて旧暦)作曲。同年12月6日、モスクワでN.ルビンシテインの指揮によって初演。
1880年1月4日~5月15日(この稿の表記は、すべて旧暦)作曲。同年12月6日、モスクワでN.ルビンシテインの指揮によって初演。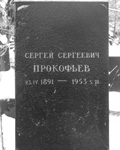 苛烈な戦いが繰り広げられていたロシア。プロコフィエフは映画監督エイゼンシュテインと共に、モスクワから遠く離れた中央アジアのカザフスタン共和国の首都、アルマ・アタ(現在のアルマトイ)にいた。戦火を避けての疎開である。そしてこの地で、エイゼンシュテインが撮影を進める《イワン雷帝》の音楽を作曲する。ロシア革命を避けて出国したプロコフィエフが、ソ連に「帰国」してからおおよそ10年が経つ頃のことだ。
苛烈な戦いが繰り広げられていたロシア。プロコフィエフは映画監督エイゼンシュテインと共に、モスクワから遠く離れた中央アジアのカザフスタン共和国の首都、アルマ・アタ(現在のアルマトイ)にいた。戦火を避けての疎開である。そしてこの地で、エイゼンシュテインが撮影を進める《イワン雷帝》の音楽を作曲する。ロシア革命を避けて出国したプロコフィエフが、ソ連に「帰国」してからおおよそ10年が経つ頃のことだ。